最近の採用手法の基本はどこにありますか?
以前と比べて何か変わりましたか?
なにか特徴はあるのですか?
派遣会社で長い間、採用担当をしています。
今はおもに母集団形成の仕事を担当しています!
みなさんの参考になれば、とても嬉しいです。
✅採用における自社サイト(オウンドメディア)
✅オウンドメディアを通してできること
✅オウンドメディアを使うメリットとデメリット
僕が採用を担当するようになって、もう20年が経過しました。
この20年間で、採用トレンドの変化をいくつか経験してきました。
- 求人誌から求人サイトへのトレンド転換
- 採用におけるPDCAサイクルの確立・運用
- 求人メディアにおける課金の変化
- 自社採用サイト(オウンドメディア)の活用
トレンド変化① 求人誌から求人サイトへのトレンド転換

インターネットが普及するより以前は「求人誌」を使った採用活動がトレンドでした。
若い世代の人にはなかなか想像が付かないことかもしれません。
求人誌に掲載したとしても、応募が来る・来ないは、何よりも「運」が先行すると言えます。
- 特定の求人誌が応募者の目に止まることは「運」
- その求人誌の中で自社の原稿が掲載されているページが応募者の目に止まることは「運」
- 開いたページの中で自社の原稿に目が行くことは「運」
- その原稿を見てもらった上で、応募してもらうことも「運」の要素が強い
- そのページに掲載される他社の案件も「運」の要素が強い
そのために、企業として「運」を最大限上げるように取り組むべきセオリーがいくつかありました。
うちの会社はとにかく大きな原稿で掲載していました。
原稿が発見される確率を上げる点では重要な取り組みですね!
複数の求人誌に繰り返し掲載していました。
より多くの人に見てもらう確率を上げる点では重要な取り組みです。
掲載場所、待遇・原稿の見た目など、他社よりも目を惹く掲載を心がけていました。
それは応募してくれる確率を上げる点では重要な取り組みです。
でも、やっぱり結局のところは「運」の要素の方が強いと言えるのです。
また、求人誌はアナログなものなので精度の高い分析をするのにも限度があります。
掲載が終わった後に、正確な分析ができないことが難点なのです。
結果的に、インターネットの普及が採用活動に大きな変化をもたらしたのです。
インターネットのなかでも、とくにスマートフォンの普及がもたらした影響は大きかったですね。
ハード面でもソフト面でも大きく進化して、いろいろな角度から分析をすることが可能になりました。
・応募獲得できた数(コンバージョン)
・閲覧から応募に変わった数
・応募しなかった理由(どこで離脱しているか)
それだけではなく、だいたいの年齢や性別、そしてどこからサイトを閲覧をしているかといった分析も可能になったのです。
トレンド変化② 採用におけるPDCAサイクルの確立・運用
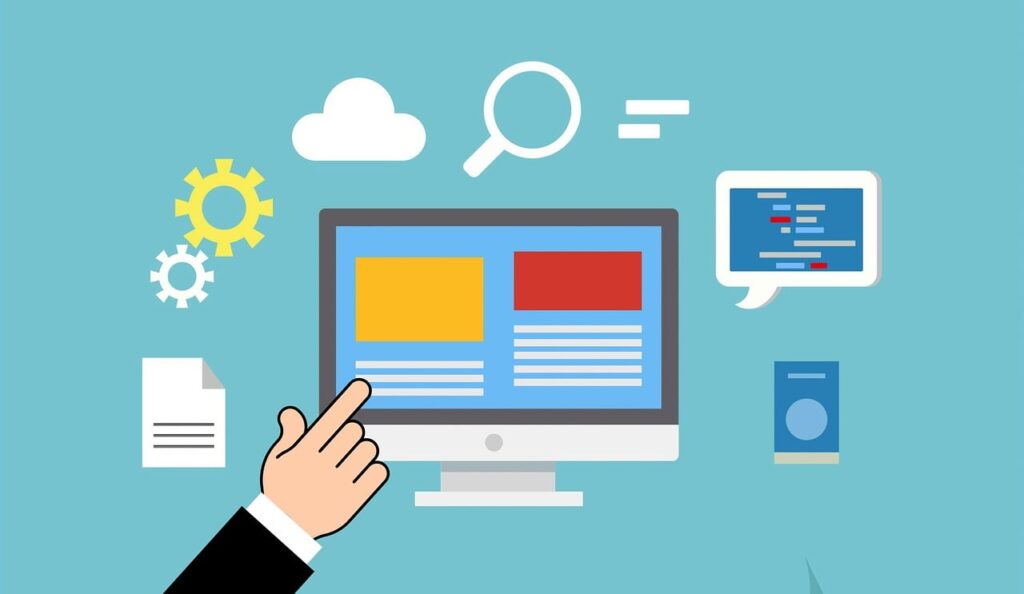
求人サイトが主流のあいだの分析は正直大した内容ではありませんでした。
分析が曖昧なものなので、きちんとしたPDCAサイクルも大した内容ではなく、しっかり運用できませんでした。
当時の運用例としてよくあったケースは、
- いくつかの求人誌に掲載をしてみた
- 反応のチェック・確認
- 反応が良かったところは引き続き掲載
- 反応が悪かったところは次回の掲載すべきかどうかを検討
といったことや、
- 同じ求人誌のなかで大きさやデザインを変えて掲載してみた
- 反応のチェック・確認
- どういったものが反応が良かったのかを検証
- 次回の掲載に生かす
といったことが挙げられます。
誌面に掲載した分析は、数字で把握できないことも多いです。
数字で確認できないということは、データに基づかない直感だとか感覚的なものが含まれるということです。
インターネットが普及・進化することで、いろいろな細かい分析が可能になりました。
正確な分析ができることで、より具体的なPDCAサイクルが運用できる。
それだけ劇的に変わったのだと言えます。
トレンド変化③ 求人サイトの本質が大きく変化

求人サイト自体も、以前と比べて大きく変わってしまいました。
✅タウンワーク
✅とらばーゆ
✅doda
✅リクナビ
✅はたらこねっと
✅バイトル
もちろん、上記のサイトのように運営歴の長い、良質な求人サイトもたくさんあります。
たくさんの業界・業種が閲覧できるオールラウンダー的な求人サイトがある。
特定の業種・業界に特化した特化型の求人サイトがある。
求人サイトの黎明期は特化型サイトの存在はありませんでした。
採用が難しい時代になると、キーポイントになるのは求人広告費。
広告掲載にはかならず経費がかかるので、もう少し安い価格で自社サイトを運営する会社が出てきはじめました。
それが自社採用サイト(オウンドメディア)への転換です。
たとえば、自社の募集案件だけが掲載されている冊子や(求人)サイトをオウンドメディアと呼びます。
メジャーな求人サイトは、非常に大きな集客力を持っています。
SEO対策ができている、大きなドメインパワーを持っているからだけではありません。
大きな集客力があるからこそ、掲載をお願いする会社も比例して多いのです。
逆から見れば、そのサイトという土俵にはライバルとなる会社がたくさん募集情報を掲載しています。
そのような状況のなか、自社の案件を見てもらって、さらに応募をしてもらうまでの間の損失も相当あると言えます。
- 他社の求人募集による応募者離脱の防止
- 求人広告費の有効活用
- 自社案件だけを見てもらいたいという発想
こうした背景から、業界を問わず自社採用サイト(オウンドメディア)の活用が進んでいるのです。
トレンド変化④ 課金システムの変化

求人広告の掲載に対する広告費の支払い方法にも変化が生じました。
今までは掲載したものに対する課金となる「掲載課金」のスタイルが中心でしたが、最近は違います。
| 応募課金 | 1件の応募があるごとに所定の金額の広告費が課金となる掲載パターン |
| 採用課金 | 1件の採用があるごとに所定の金額の広告費が課金となる掲載パターン |
| クリック課金 | 原稿が1回クリックされる(詳細表示)ごとに所定の金額の広告費が課金となるパターン |
応募課金・採用課金プランの特徴やメリット・デメリット、具体的な課金の金額については別記事をお読みください。
応募課金・採用課金・クリック課金、すべてに言えるのは、インターネットメディアだからこそ普及したプランだということです。
トレンド変化⑤ 自社採用サイト(オウンドメディア)の活用
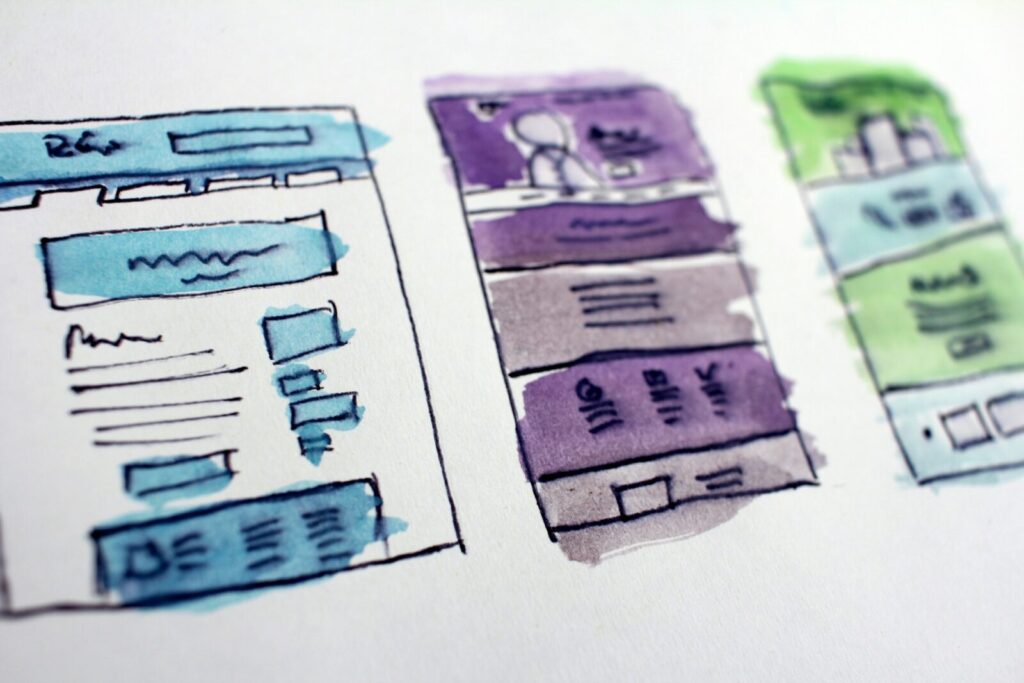
最近は自社で採用サイトを作る会社も徐々に増えてきました。
オウンドメディアとは自社の情報を発信するメディアだと考えれば十分です。
紙メディアであったり、ネットメディアであったり、形態はいろいろです。
ただし、一般的にはネットメディアを指す方が多いと言えます。
一般的に言われるオウンドメディアのメリット・デメリットについて考えてみました。
・随時、公開や修正が可能なので、急な人材募集にも柔軟に対応することができる
・案件掲載数に関わらず月額の求人広告費は一定額に抑えることができる
・自社の求人案件のみの掲載しかないので他社募集案件への流出を防ぐことができる
・応募者管理機能の付いた採用ホームページもいくつかリリースされている
・一定の成果が出るまでにある程度の期間が必要となる(即効性がない)
・成果を出すには労力とコストがかかる(求人広告費以外の要素が欠かせない)
・オウンドメディアだけで採用サイクルを回していくことは非常に困難(採用ボリュームが少ない)
・システムトラブルなどに対応できるスタッフや部門が必要となる
メリットとデメリットを比較したときに、得られるメリットの方が大きいのです。
ちなみにここでいうオウンドメディアとは、自社の求人案件だけを掲載した自社の求人サイトを指しています。
【本記事のまとめ】採用手法の基本は自社採用サイトに移行しているが課題も多く、現段階では他メディアとの併用が理想

自社採用サイトを運用する会社はたしかに増加傾向にあります。
そして、そのサイトにかける経費も増加傾向にあります。かけるべき経費も増加傾向です。
それが2025年時点の全体的なトレンドでもあります。
自社採用サイトの活用が主流にはなっているとは言っても、一般的な求人サイトがなくなる可能性は今のところゼロに近いです。
自社のサイトだけで採用を完璧に回していくには莫大な労力とコストがかかるのです。
オウンドメディアの成功の一番の近道は、あくまでもメディアミックス。
一般的な求人サイトへの出稿と相関関係にあるので、求人サイトとの併用での掲載がベストなのです。
目安としてはオウンドメディアだけで全体応募の7割くらいを占めることができるまでは、併用するのがベストです。
求人広告費と実際の応募シェア率を見てみました。
・全応募者のなかでオウンドメディア経由の占める割合(22%)
・全採用者のなかでオウンドメディア経由の占める割合(20%)
・全応募者のなかでオウンドメディア経由の占める割合(20%)
・全採用者のなかでオウンドメディア経由の占める割合(15%)
このような状況ではオウンドメディアだけでの運用はまだまだ先のことだと言えます。
ただ、オウンドの方が少しだけ効率よく母集団形成ができるという明かりも見えました。
さらに数年後、改めてリサーチしてみました。
・全応募者のなかでオウンドメディア経由の占める割合(57%)
・全採用者のなかでオウンドメディア経由の占める割合(53%)
✅採用における自社サイト(オウンドメディア)
✅オウンドメディアを通してできること
✅オウンドメディアを使うメリットとデメリット
・オウンドメディアを活用する会社は増加傾向にある
・オウンドメディアは長期的に運用する必要がある上、コストや労力も相当かかる
・運営が軌道に乗るまでは一般的な求人サイトをうまく併用すべき(オウンド一本では貧弱)
・オウンドメディアにもメリット、デメリットはあるがメリットのほうが大きい
本日は以上です。

